最近少し涼しくなり、過ごしやすくなりましたね。
暑さから解放されてほっとしています。
今回は、ひと夏を過ごして実感した、真夏のぬか床のベストな管理法をお伝えします。
人間にとって暑いと感じるときは、ぬか床にとっても快適な環境ではないはずです(生き物ですから)。
ですので、ぬか床管理のカギは、猛暑の時期をいかにうまく乗り切るかにあると思っていました。
夏を乗り切れば、ぬか床ユーザーとして一人前だ!と思い、うまく乗り越えるべくいろいろな方法を模索しました。
そして編み出したベストな方法は、
・エアコンを消して外出する日中は冷蔵庫へ
・夜間やエアコンをつけている時間帯は常温でOK
です。
以下、詳しくお話しします。
わが家のぬか床の環境
まず、前提として、わが家のぬか床をとりまく環境をお伝えします。
ぬか床は、普段は流し台の下で管理しています。
夕食にぬか漬けを食べ、そのときに翌日の分を漬けるので、24時間ぐらい漬けていることになります。
真夏だと、在宅時はエアコンをつけているので室温は25度ぐらいに保たれていますが、エアコンを消すと30度ぐらいまで上がっていると思われます。
模索の日々
初夏
5月下旬ごろ、だいぶ暑くなってきたなと感じ始めたころから、ぬか床の活動が活発になったように感じました。
野菜の切り方や漬け時間等は変えていないのに、明らかによく漬かるようになりました。
ただ、ぬか床自体に異常はなく、意外と大丈夫なのだなと感じました。
このまま常温で夏を乗り切れるのでは?と思っていました。
夏本番
しかし、6月に入って早すぎる梅雨明けを迎え、エアコンをつけたいほどの暑さになると、「漬かりすぎ」と感じるようになりました。
きゅうりなどは完全に変色し、水分が抜けてふにゃふにゃになっていました(笑)完全に古漬け状態です。
よく漬かったぬか漬けもおいしいですが、わが家ではおかずの一品としてぬか漬けを食べているので、古漬け状態では味が濃すぎです。
そこで、漬かり具合を調整するために、朝出かける前にぬか床を冷蔵庫の野菜室に入れることにしました。
ちなみに、このときは確か室温25度を超えていたのですが、ぬか床自体には問題はありませんでした。
菌の活動が活発になるのかぬかがだいぶゆるくなりますが、こまめにたしぬかをしたり水分を取ったりすれば大丈夫でした。
真夏のぬか床のベストな管理法
結果的に、この方法は大成功で、好みの漬かり具合にすることができました。
よって、真夏のぬか床管理は、
・エアコンを消して外出する日中は冷蔵庫へ
・夜間やエアコンをつけている時間帯は常温に置く
に落ち着きました。
なお、ずっと冷蔵庫に入れておけば楽かなとも思ったのですが、そうすると発酵が抑えられてしまい、あまりおいしく漬かりませんでした。
そして、冷蔵庫から出したぬか床は、冷たく固くなって明らかに元気がないのです(笑)
ぬか床も生き物ですので、時々は常温に戻してあげたほうがいいのではないかという結論に至りました。
また、冷房をつけて常温で置く場合は、夜に漬けたあと朝にも一度かき混ぜてあげると調子がいいように感じました。
外が猛暑の日に一日放置すると、白い産膜酵母がびっしりと張っていて焦ったことがあります。
(産膜酵母自体に害はないですが、産膜酵母が発生するということはかき混ぜが足りないということです。)
それから、気温が高いほどぬか床はゆるくなる傾向にあります。
あまりに水分が多くなると雑菌が繁殖しやすいので、こまめにたしぬかをしたりペーパーで水分を取ったりするなど、丁寧なお世話が必要です。
まとめ
ぬか床は、毎日かき混ぜてさえいれば、気温が高くなっても意外と大丈夫です。
ただ、漬かり具合と管理の楽さを考えると、日中は冷蔵庫に入れるのがおすすめです。
なお、気温のほか、野菜の種類や切り方によっても漬かり具合は変わります。
色々な条件で試してみて、ご自分の好みの漬け方を模索してください!
おまけ:漬かりすぎたぬか漬けの活用法
うっかり暑い中ぬか床を放置してしまい、野菜が漬かりすぎてしまった場合は、刻んでサラダや冷や奴のトッピングにするのがおすすめです。
特に、キュウリやオクラがぴったりですよ!
ぬか漬けをトッピングした上から、ごま油やオリーブオイルをかけてもおいしいです。
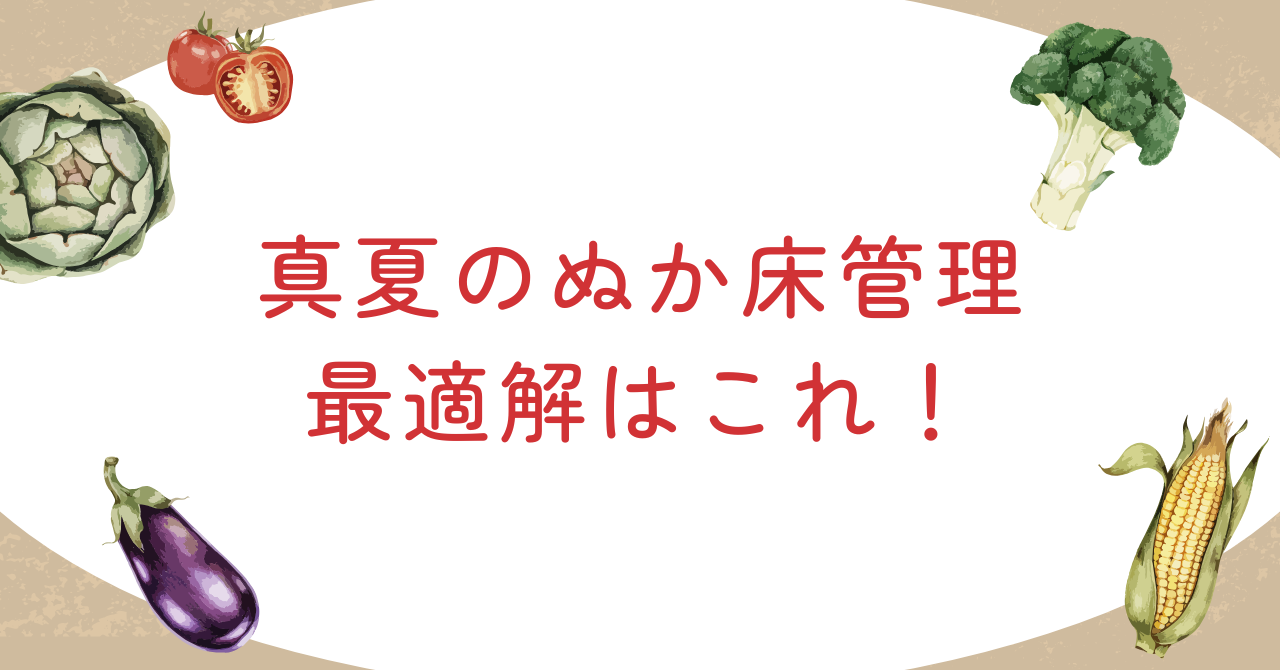
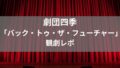

コメント